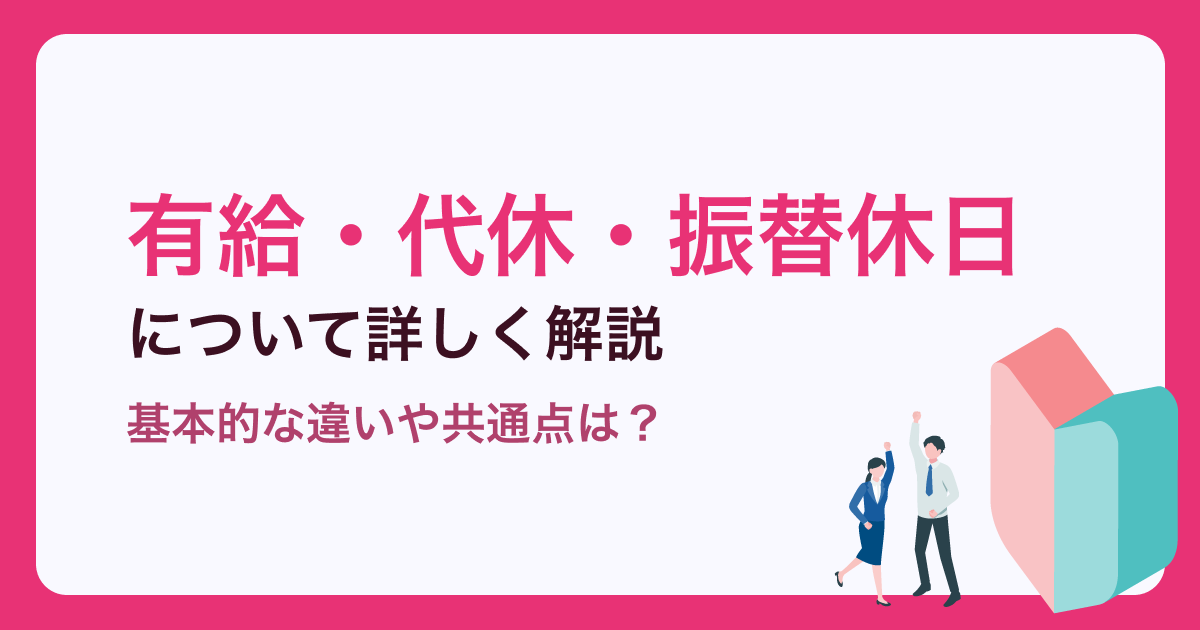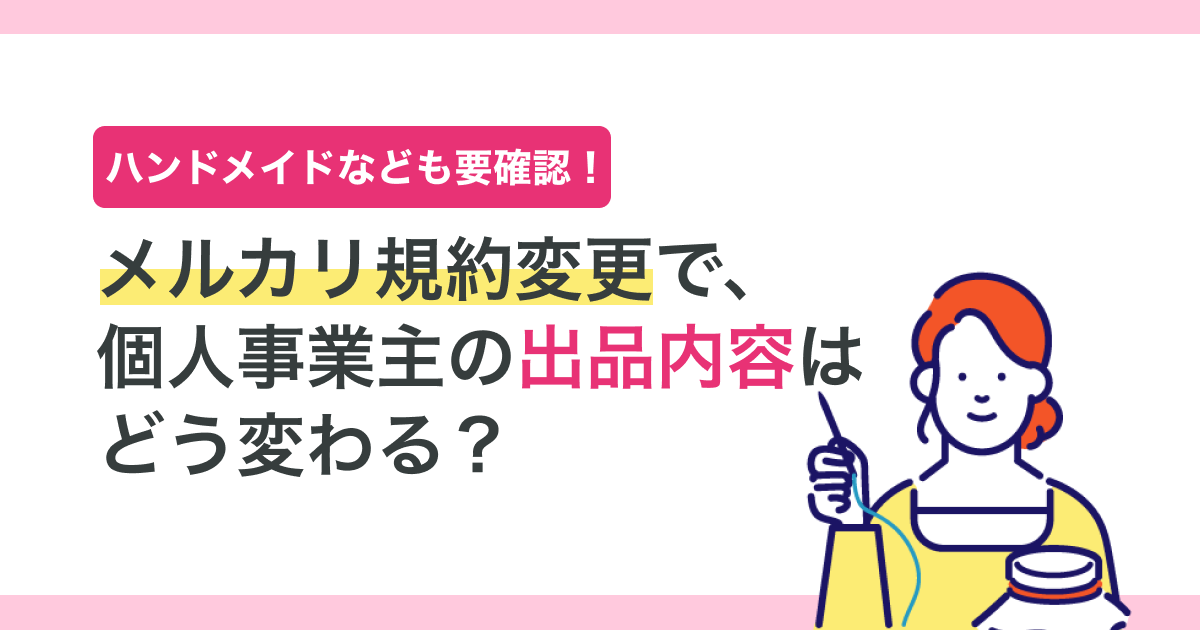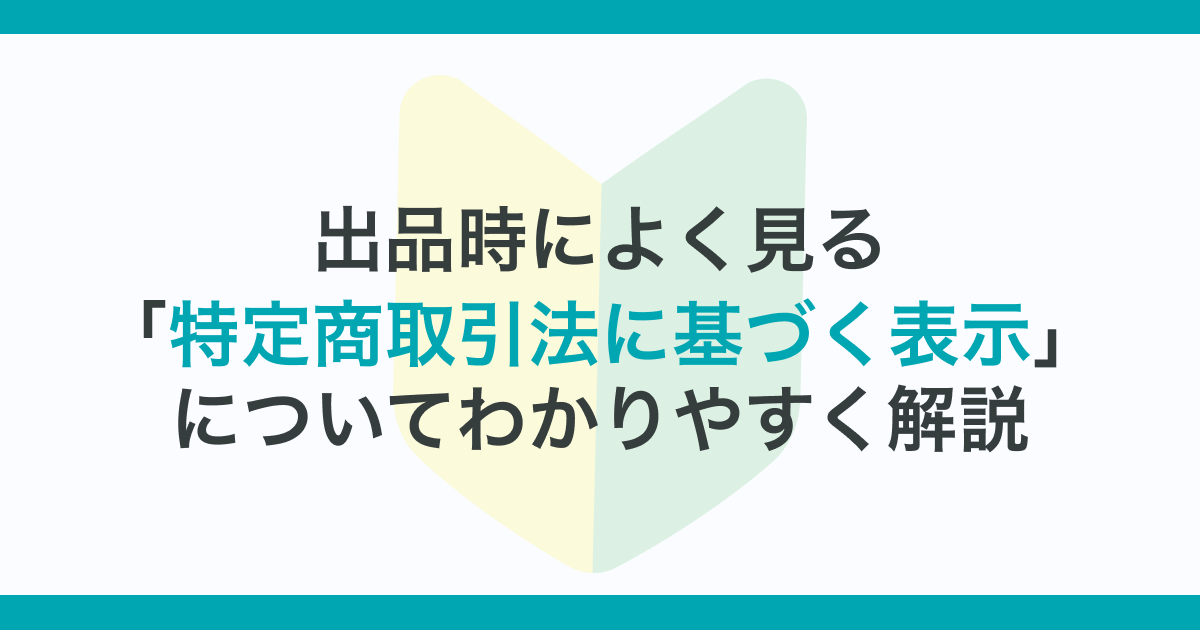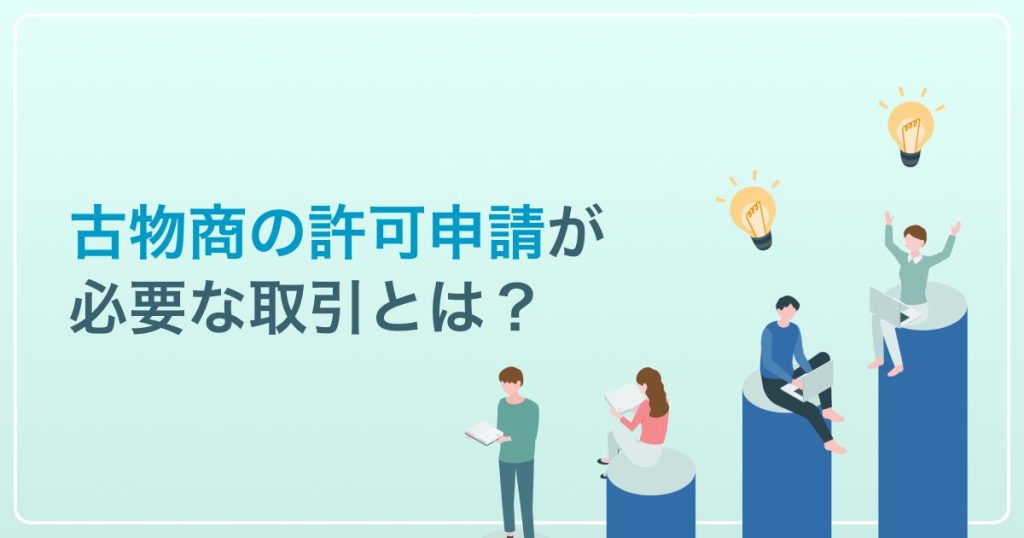
古物商許可は、古物を売買する際には必須の許可です。しかし、古物の定義は何か?個人間の売買では必要なのか?など、細かい内容はあまり知られていません。本記事では、許可が必要な商品や取引について、詳しく説明していきます。
目次
古物商の許可申請が必要な取引とは
古物商許可については、「中古品を取り扱う際に必要な許可」ということはよく知られていますが、どこまでが古物なのか?どういった取引をするときに必要なのか?を細かに理解している方は案外少ないのではないでしょうか。
本記事では、古物商の許可申請が必要な古物や取引について、具体的なパターンも示しながら詳しく説明していきます。
古物商許可とは?
古物商許可は、営業として中古品を売買する際に必要となる許可で、古物営業法により定められているものです。なぜ古物営業に許可が必要なのかというと、古物の売買においてはその性質上、盗品が紛れ込む可能性が高いため、法規制により流通の実態を管理する必要がある、ということが背景にあります。
無許可で古物営業を行った場合には、懲役3年以下または100万円以下の罰金が科されるなど、非常に重い罰則が定められています。
なお、「古物営業」には1号営業から3号営業までの3種類があり、以下のように定められています。
1号:
古物を売買・交換、または委託を受けて売買・交換する営業
2号:
古物市場(古物商間で行われるオークションなど)を経営する営業
3号:
古物売買が行われるインターネットオークションの運営者
古物=中古品というイメージが一般的ですが、法律上、古物の定義は以下のように定められています。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これは「一度は消費者の手に渡ったが未使用のもの」のことを指しており、見た目上は新品でも法律上は古物として扱われます。あくまで一般消費者の手に渡ったかどうかが重要となりますので、業者間のみで流通するぶんには古物とはなりません。
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
- 物の本来の性質が変化しない程度の修理を行うことを指しており、絵画の表面を補修する、刀を研ぎ直すなどがこれにあたります。
また、古物は品目によって13種類に分類されており、取り扱う品目を事前に申請する必要があります。
| 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
| 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
| 自動車 | その部分品を含みます。 |
| 自動二輪車及び 原動機付自転車 | これらの部分品を含みます。 |
| 自転車類 | その部分品を含みます。 |
| 写真機類 | 写真機、光学器等 |
| 事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
| 機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
| 道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
| 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
| 書籍 | |
| 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
なお、以下のものは、盗難被害に遭う可能性が低いことや古物として流通しにくいことから、古物に該当しないとされています。
- 大型機械の一部(船舶、航空機、鉄道車両など)
- 廃品(空き缶、空き瓶、鉄くずなど)
- 美術品としての価値がない古銭
- 消費して無くなるもの(化粧品、薬品、お酒など)
- 庭石、石灯籠
これらを取り扱う機会は多くはないかと思いますので、実質的にほぼすべての品目が古物にあたると考えておいたほうがよいでしょう。
許可が必要なケース
許可が必要になるのは、ひとことで言えば「業として古物を取り扱う」ケースです。
つまり、営利を目的として反復継続して古物の売買を行うかどうか、また、大量に売買するかどうかなど、目的や頻度、規模が主な判断基準となります。
過去の判例では、営利目的の意思を持って取引をした場合は、たとえ反復性や継続性がなくても(1回の取引であっても)、業として行ったと判断されたケースもあります。
取引の形態という面では、単純に仕入れた古物をそのまま販売することはもちろん、それ以外の方法でも許可が必要となる場合があります。
【許可が必要となる取引例】
- 古物を買い取って販売する
- 買い取った古物を修理して販売する(本来の性質が変化しない程度の修理)
- 買い取った古物の部品など、一部を販売する
- 中古車から使用可能な部品を取り出してその部品を販売する場合などが該当します。
- 古物を別の物品と交換する形で仕入・販売する
- 古物を買い取る際に現金ではなくクーポン券や割引券などを提供する場合などが該当します。なお、「別の物品」が古物か新品かは問いません。
- 買い取った古物を有償でレンタルする
- 中古車のレンタカーなどが該当します。
- 手数料を得て古物を委託販売する
- 質屋が顧客から預かった古物を販売し手数料を得る、他者から依頼を受けて代理で販売し手数料を得る場合などが該当します。
- 国内で買い取った古物を国外で販売する
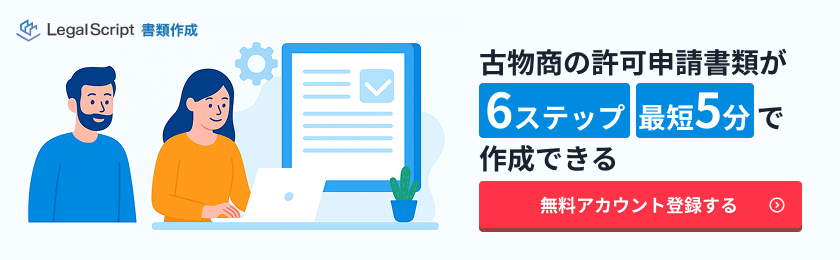
許可が不要なケース
一方、業として行わないケースや盗品が紛れ込む可能性が低いと考えられるケースでは、古物商許可は不要とされています。
【許可が不要な取引例】
- 自己使用していた不用品を販売する
- 自己使用と言いながら実際は転売のために所持していた場合は許可が必要となります。
- 新品で購入したものを転売する
- 顧客に販売した商品を直接その顧客から買い戻す
- 顧客がさらに別の者に転売しているなど、販売した顧客以外から買い戻す場合は許可が必要となります。
- 古物を無償で譲り受ける/無償で譲り受けたものを販売する
- 廃品の無料回収などがこれにあたります。別途、廃棄物処理等に関する許可が必要となる可能性があります。
- 処分手数料を徴収して引き取ったものを販売する
- 自身が外国で購入したものを国内で販売する
- 他者が輸入したものを日本国内で買い取って販売する場合は許可が必要となります。
まとめ
- 古物商許可は盗品流通防止の観点から設けられており、無許可営業には重い罰則が定められている。
- 業として行う古物取引に該当するかどうかは、取引の目的、頻度、規模(数量)を基準に判断される。
- 取引の形態や方法によっても古物商許可の要否が異なる。
古物商許可は、ビジネスとして古物取引を行う場合には必須の許可です。自身のビジネスを安全・公正に行うためにも、取扱商品や取引形態が古物商に該当するかを事前にしっかり確認し、スムーズな許可申請を行いましょう。
こちらの記事もおすすめです!