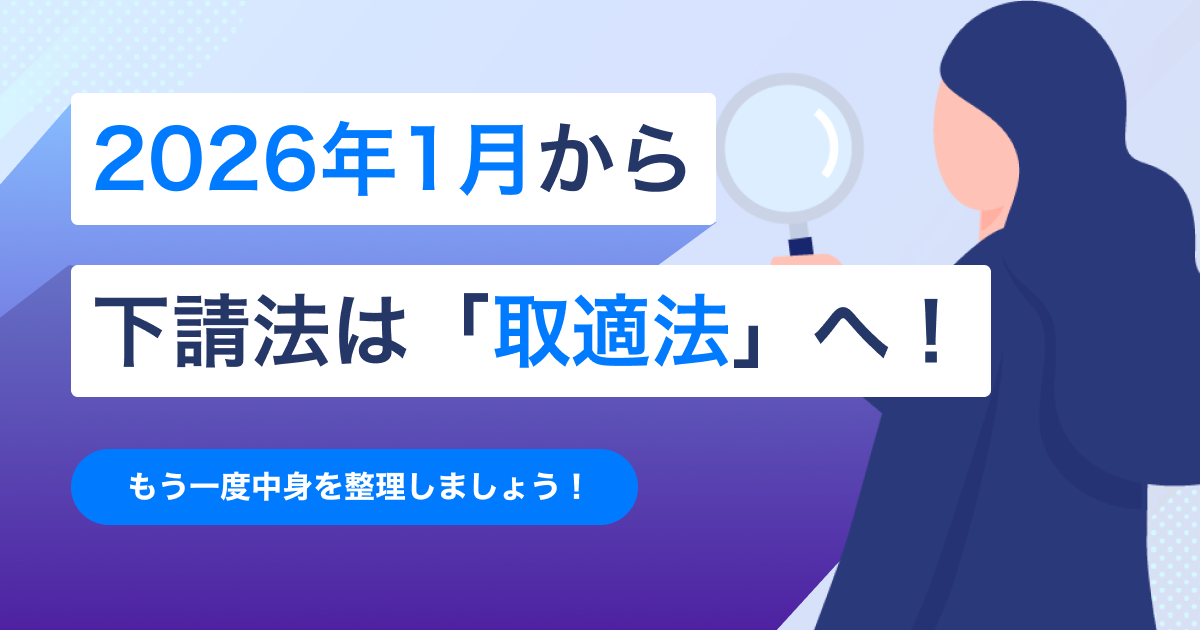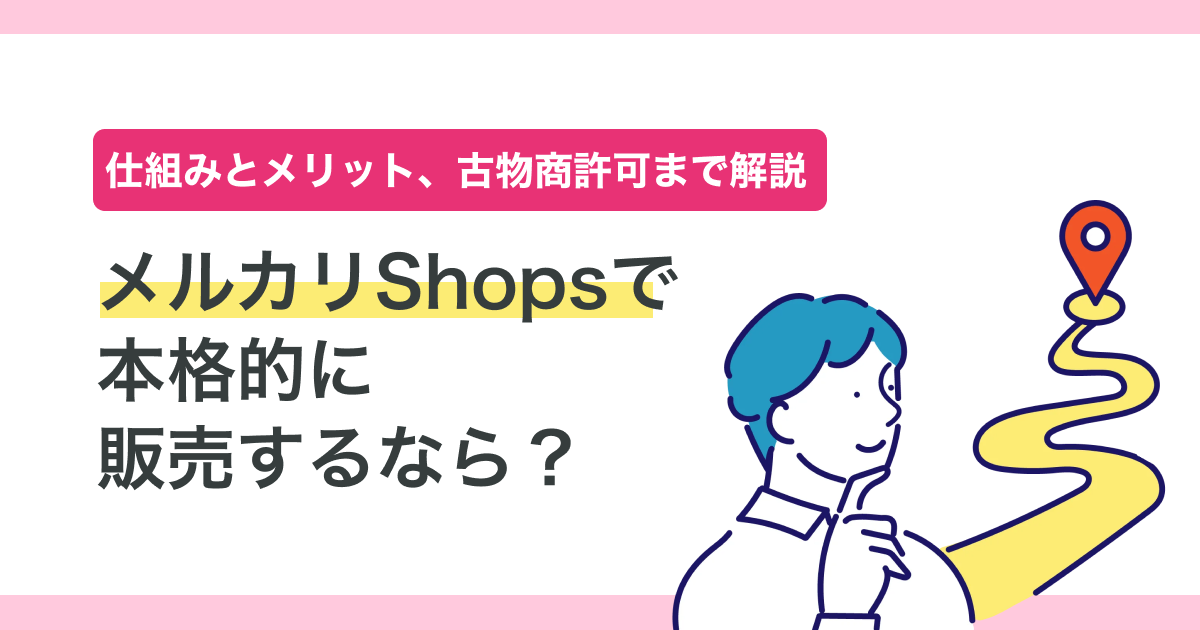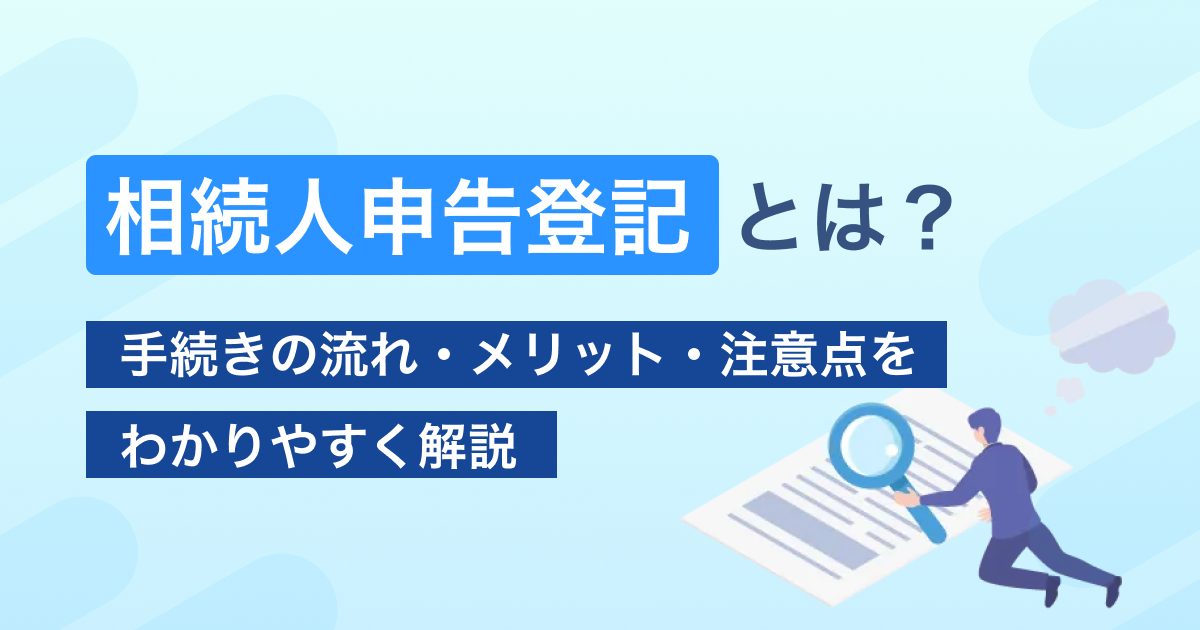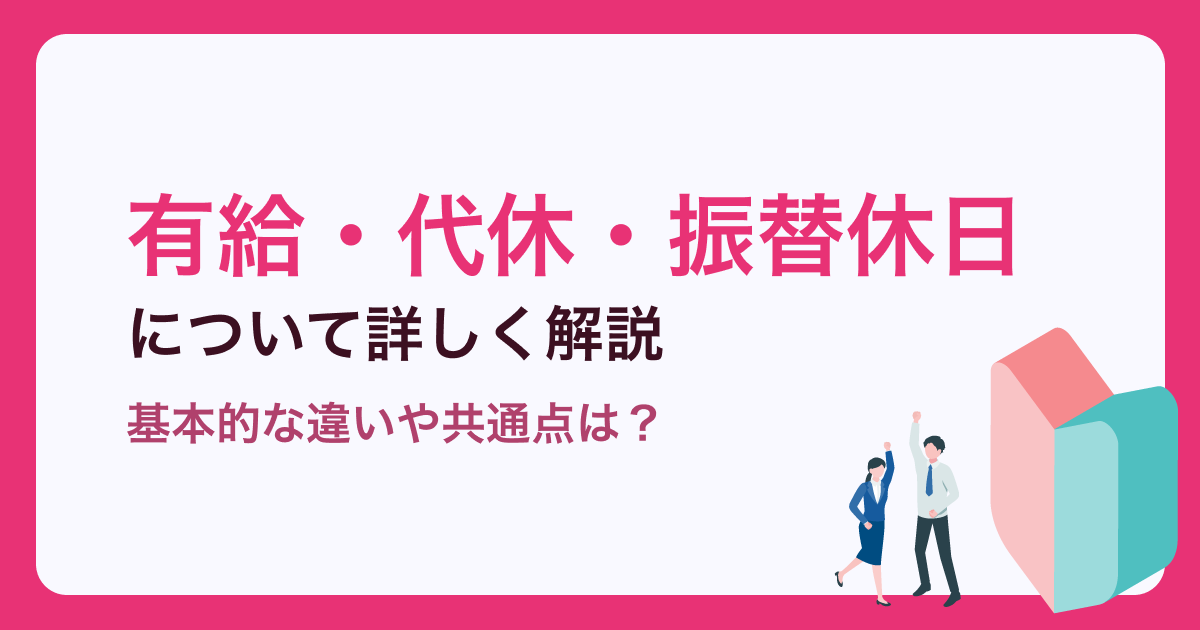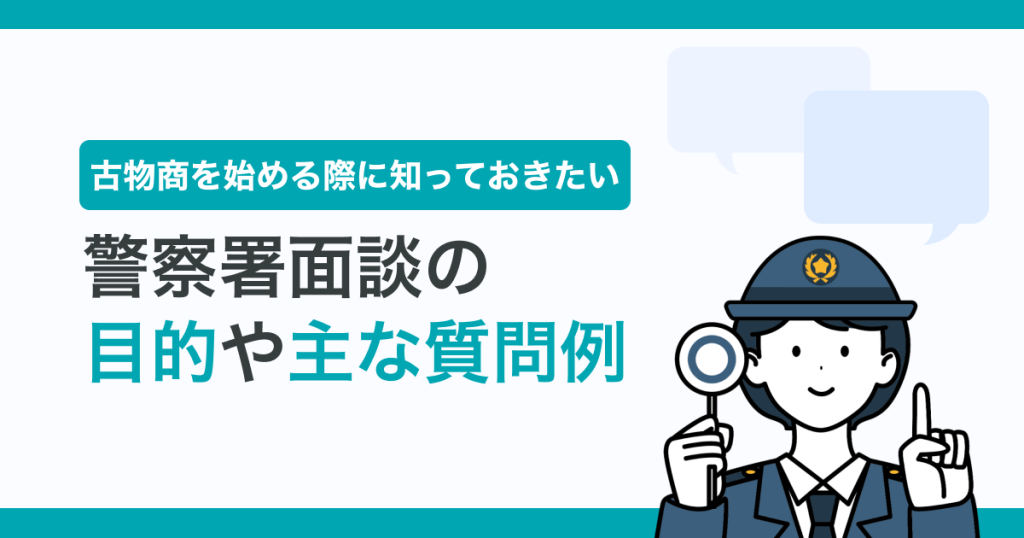
目次
警察署での面談の目的と心構え
古物商の許可申請では、書類提出後に警察署(公安委員会)の面談が行われるのが一般的です。この面談は、申請者が法令を理解し、古物営業を適切に行えるかどうかを確認するためのものです。申請書類だけでは判断できない営業実態や、本人の意思・管理体制などを直接確認するのが目的です。
初心者の方にとっては少し緊張する場面かもしれませんが、誠実に答えれば問題ありません。警察官はあくまで確認のために質問しているので、「完璧な答え」よりも「嘘をつかないこと」が重要です。
主な質問例とその法的根拠・回答例・警察の意図
以下に、面談でよくある質問をテーマ別に整理し、その法的背景や警察側の確認意図、行政書士としての回答例を解説します。
1. 取扱う古物についての質問
- 質問例: どのような古物を取り扱う予定ですか?また、なぜその品目を選んだのですか?
- 意図: 古物営業法第2条に基づく「古物」の定義に該当するか確認。また、業務の実現可能性や営業実態が伴っているかを判断するための参考として選定理由を尋ねる。
- 回答のポイント: 「中古のスマートフォンやパソコン」など具体的に。新品のみ、仕入先が法人のみなどは古物に該当しない場合もある。選定理由としては「以前から趣味で扱っており知識がある」「需要が高く、利益を見込めるから」など実情に基づいたものを答えると良い。「中古のスマートフォンやパソコン」など具体的に。新品のみ、仕入先が法人のみなどは古物に該当しない場合もある。
2. 営業所(事務所)に関する質問
- 質問例: 営業所はどこですか?常駐する人はいますか?事務所は個別に区画され、鍵はかかりますか?
- 意図: 実体ある独立した拠点があるか、古物営業法第3条の要件を満たすか確認。特に鍵の有無や区画の独立性は、古物の安全な保管や台帳管理ができる環境かどうかを判断する材料となります。
- 回答のポイント: 自宅なら「玄関に許可票掲示、帳簿保管場所あり」、レンタルオフィスなら「専有個室で使用承諾取得済、鍵付きでセキュリティ確保」など、物理的・管理的独立性を明示する。自宅なら「玄関に許可票掲示、帳簿保管場所あり」、レンタルオフィスなら「専有個室で使用承諾取得済」など。
3. 仕入れ・買取方法に関する質問
- 質問例: どのように仕入れますか?本人確認はどう行いますか?お客様から出張買取(行商)はしますか?(自動車・バイクの場合)どうやって仕入れますか?仕入れた車両の保管場所はありますか?
- 意図: 古物営業法第15条などによる確認義務の理解度。出張買取の場合の本人確認・記録義務の徹底、ならびに自動車等のように保管義務が生じる古物の取り扱い状況を確認するため。
- 回答のポイント: 「身分証を確認し、古物台帳に記載する」など具体的に。フリマアプリ経由は要注意。出張買取を行う場合は「本人確認は現場で行い、帳簿に記録する」、自動車等を扱う場合は「陸運局での手続きや車庫の確保も済んでいる」など、実態と対策を丁寧に説明する。「身分証を確認し、古物台帳に記載する」など具体的に。フリマアプリ経由は要注意。
4. 販売方法に関する質問
- 質問例: 販売はどう行いますか?ネット販売の場合どのようなサイトを使いますか?
- 意図: 管理の実態や営業形態を確認。
- 回答のポイント: 「自社サイトおよびヤフオク、メルカリを使用予定。管理は在宅で行う」など実情に即した回答を。
5. 管理者や経験・知識に関する質問
- 質問例: 古物営業の経験はありますか?管理者としての知識は?(法人の場合)営業所の管理者は他の営業所と兼任していませんね?(法人の場合)管理者の方はちゃんとその営業所に通勤できますか?遠方に住んでいませんか?(申請者が外国籍の場合)日本語で業務できますか?
- 意図: 古物営業法第13条に基づき、管理責任者の適格性を確認。また、管理者が実際にその営業所を適切に監督できるか(兼任不可・通勤可能性)、外国籍の申請者については業務遂行に必要な日本語能力を持つかを判断するため。
- 回答のポイント: 経験がなければ「今後研修や行政書士のサポートを受けて対応する」など誠実に。法人の場合は「管理者は専任で、その営業所に通勤可能です」と明言できるように。外国籍の場合は「日本語での接客や帳簿作成は問題なく対応可能です」と示す。
6. 提出書類の確認に関する質問
- 質問例: 賃貸契約書に使用目的が記載されていますか?誓約書の内容は理解していますか?住民票の住所と申請書の住所が違いますが修正できますか?法人の役員欄に漏れはありませんか?
- 意図: 書類の真正性と理解度を確認。特に、申請書と住民票等の記載内容の不一致や、法人申請時の役員情報の漏れといった形式的な不備がないかを重点的にチェック。
- 回答のポイント: 「書面はすべて確認済。必要に応じて再提出や修正届出も対応可能です」「役員欄は定款・登記簿に基づき正確に記載しています」など、誤りがあれば修正対応の意思を、正確であれば根拠を示して答える。「書面はすべて確認済。必要に応じて再提出も可能」など柔軟に答える。
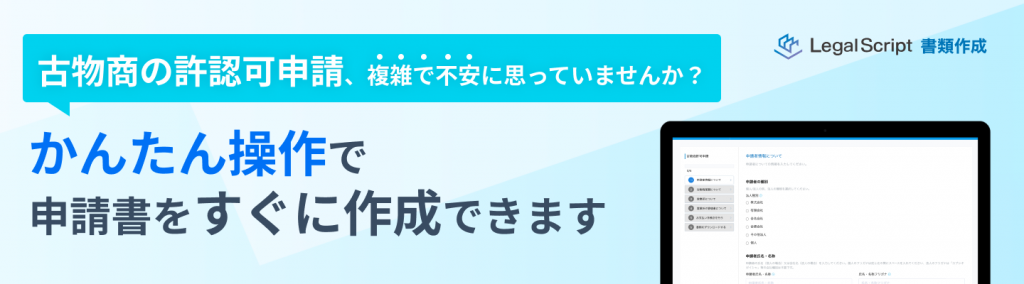
事前に準備すべきことまとめ
面談をスムーズに進めるためには、以下のポイントを事前に確認・準備しておきましょう。
- 営業所の使用実態を示す写真やレイアウト図の準備
- 賃貸契約書・使用承諾書の写し
- 古物台帳のサンプル(用意できれば)
- 仕入・販売・本人確認の具体的フローを簡単にメモしておく
- 管理者の対応方針を整理しておく
行政書士に依頼している場合は、想定問答や警察署ごとの傾向も共有してもらうと安心です。
警察署での面談は、申請者がきちんと準備していれば恐れる必要はありません。重要なのは、「古物営業をまじめに取り組む姿勢」を示すことです。
まとめ
警察署での質問ややり取りは、決して意地悪な面接試験ではなく「申請内容の確認作業」です。ポイントを押さえて準備すれば誰でも自己対応可能です。本記事を参考に、想定問答と法的根拠を踏まえた上で臨めば、きっとスムーズに許可申請を乗り切れるでしょう。古物営業法の目的である「盗品等の防止」に協力するつもりで、真摯かつ自信を持って対応してください。