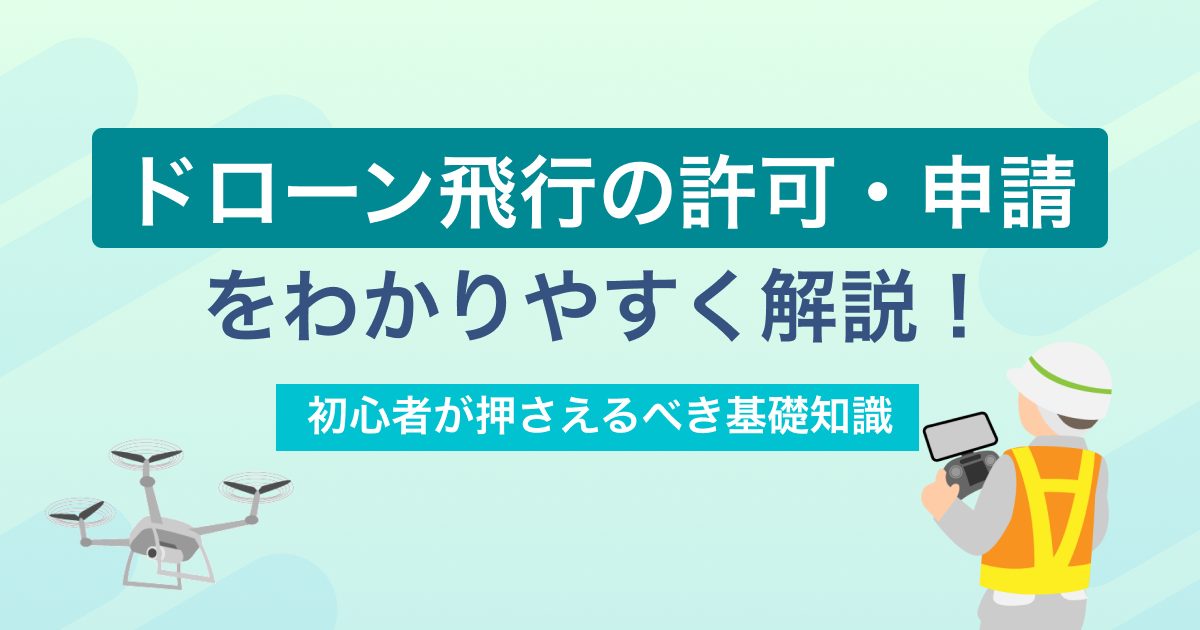会社の経営を進めていくうえでは、従業員を解雇したい、あるいは、せざるを得ない場面も出てくるものですが、解雇には労働者保護の観点から様々な制限が設けられています。
今回は、解雇について知っておくべきことや、実際に従業員を解雇する場合の手続きについて解説します。
目次
解雇とは
解雇とは、従業員をいわゆる「クビ」にすることですが、まずは、解雇が法的にどのような行為であるのか、また、解雇の種類について説明します。
解雇とはどのような行為か
解雇とは、会社側から一方的に従業員との雇用契約を終了させることです。
退職と違って、会社側からの一方的な行為であるため、解雇には様々な制限が設けられています。
なお、一般的には、解雇する前にまずは話し合いの場をもって従業員に退職を促し(退職勧奨)、それでも退職に応じない場合に解雇する流れになります。
解雇の種類
解雇は一般的に次の4種類に分けられます。
①普通解雇
次の②~④に該当しない解雇で、従業員の勤務成績が著しく悪く、かつ、指導を行っても改善が見られない場合や、健康上の理由で長期にわたって職場復帰が見込めないときなどの解雇です。
②整理解雇
会社の経営悪化によって人員整理を行うための解雇、いわゆる「リストラ」です。
この整理解雇を行うためには、判例によって確立している次の4つの要件を満たしていなければなりません。
- 整理解雇をすることに客観的な必要性(経営の悪化が深刻であるなど)があること
- 解雇を回避するために最大限の努力(役員報酬のカットや一時帰休の実施など)を行ったこと
- 解雇の対象となる人選の基準、運用が合理的に行われていること
- 労使間で十分に協議を行ったこと
③懲戒解雇
従業員が極めて悪質な規律違反をしたときに懲戒処分として行う解雇です。
④諭旨解雇
会社によっても違いがありますが、一般的には上記の懲戒解雇としてもいいところを、懲戒解雇に次ぐ処分として解雇を受け入れさせる、または、退職願を提出させて退職させることを言います。
ただし、退職願を提出させて退職させるのであれば、厳密には「諭旨退職」になります。
法律上の解雇制限
解雇は労働者の生活に大きな影響を及ぼすものであるため、労働関係法においては様々な制限があります。
各法律において、どのような制限があるのかについて説明します。
労働契約法における制限
解雇について、労働契約法では次のように規定しています。
労働契約法第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。
簡単に言えば、従業員が1度や2度の業務上のミスをしたことだけをもって解雇することはできず、従業員の落ち度や会社が被った損害など様々な事情を考慮して解雇が相当であると認められる場合のみ解雇できるということです。
その他各法における制限
そのほか、各法律では次のような解雇を禁止しています。
〔労働基準法〕
- 業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇
- 産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇
- 国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
- 労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
〔労働組合法〕
- 労働組合の組合員であることなどを理由とする解雇
〔男女雇用機会均等法〕
- 労働者の性別を理由とする解雇
- 女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇
〔育児・介護休業法〕
- 労働者が育児・介護休業などを申し出たこと、または、育児・介護休業などをしたことを理由とする解雇
※「男女雇用機会均等法」と「育児・介護休業法」は略称で、それぞれ正しくは「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」です。
解雇するために必要な手続き・注意点
従業員を解雇するためには、まず、どのような場合に解雇することがあるのかを就業規則や雇用契約書に記載しておき、従業員もそのことを認識できている状態でなければなりません。
これを前提として、実際に解雇するために必要な手続きや注意点などについて説明します。
解雇するために必要な手続き
従業員を解雇するために必要な手続きは、いつ解雇したいのかによって異なり、基本的には次の3つのいずれかになります。
①30日前までに解雇の予告をして解雇する
原則としては、解雇しようとする従業員に対して、少なくとも30日前までに解雇の予告をしたうえで解雇することになります。
この解雇予告は口頭でも有効ですが、後々のトラブルを防ぐためにも「解雇予告通知書」(解雇日や解雇の理由、解雇予告通知日などを記載)を作成して、書面で通知しておくことが重要です。
②30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払って解雇する
解雇しようとする日までに30日以上の余裕がない場合には、解雇の予告をしたうえで、30日に不足する日数分の解雇予告手当(平均賃金)を支払えば解雇できます。
この解雇予告手当を支払う場合も、後々のトラブルを防ぐために「解雇予告手当支払通知書」(解雇日や解雇予告手当の支払期日、支払金額、支払方法などを記載)作成して、書面で通知しておきます。
③30日分以上の解雇予告手当を支払って即時解雇する
すぐに解雇したい場合には、30日分以上の解雇予告手当を支払えば解雇できます。
解雇予告の対象にならない従業員
次のような従業員は、労働基準法において解雇予告の対象から除かれているため、合理的な理由があれば、解雇予告をすることなく解雇できます。
①日々雇い入れられる者
②2か月以内の期間を定めて使用される者
③季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
④試の使用期間中の者
ただし、①については1か月を超えて引き続き働くことになった場合、②および③については契約で定めた期間を超えて引き続き働くことになった場合、④については14日を超えて引き続き働くことになった場合には解雇予告の対象になります。
「解雇予告除外認定」について
従業員を解雇する場合、原則としては上記の解雇予告や解雇予告手当の支払いが必要になりますが、以下に該当する場合には労働基準監督署の認定を受けることで、解雇予告をせず、また、解雇予告手当を支払うことなく解雇することができます。
①天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合
②労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
ただし、会社側が従業員の責に帰すべき事由があると認識していても、必ず②として認定を受けられるわけではありません。認定を受けられるのは、あくまで、労働基準監督署がその従業員に事情を聴取したうえで、解雇予告の保護を与える必要がない程度に重大な責任があると判断した場合です(認定を受けられないこともあります。)。
また、この認定を受けたとしても法的な拘束力はなく、最終的に裁判に発展するリスクもあります。
まとめ
従業員を解雇するためには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要であり、かつ、上記で説明した法律に基づいた手続きを経なければなりません。
なお、適正な手続きで従業員を解雇したとしても、その後にトラブルに発展するリスクもあるため、まずは自主的な退職を促すなど解雇以外の道を模索することも重要です。